はじめに|「掛け捨て=損」って本当?
「どうせ保険料を払っても戻ってこないから、掛け捨て保険って損だよね…」
こんなイメージを持っている人は少なくありません。しかし、実は**掛け捨て保険は“使い方次第で得にもなる”**商品です。
本記事では、掛け捨て保険の仕組みやメリット・デメリットを丁寧に解説しながら、どんな人が得をして、どんな人が損をするのかを徹底分析していきます。
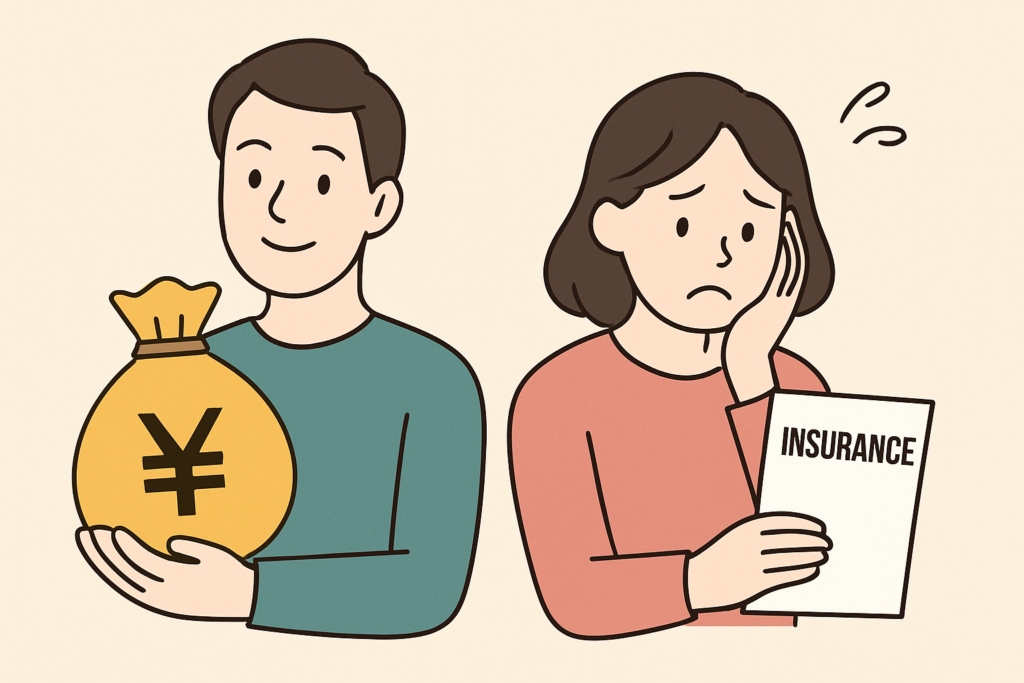
1. 掛け捨て保険とは?仕組みと特徴をおさらい
掛け捨て保険とは、保険期間中に万が一のことがあった場合に保険金が支払われる保険で、期間が満了しても保険料が戻ってこないのが特徴です。以下のような保険が掛け捨て型に分類されます。
- 定期生命保険
- 医療保険(多くが掛け捨て)
- がん保険
- 傷害保険
掛け捨てと聞くとネガティブに捉えられがちですが、「保障を得るためのコスト」として割り切れば、非常に合理的な選択となります。
2. 掛け捨て保険のメリット
① 保険料が安い
同じ保障額でも、掛け捨て保険の方が圧倒的に保険料が安いです。必要な期間だけ加入すればよいため、ライフステージに応じた柔軟な設計が可能です。
例:30歳男性が1,000万円の保障を受ける場合
- 掛け捨て定期保険:約1,500円/月
- 終身保険:約10,000円/月
② 保険料を抑えて他の資産形成に回せる
浮いた保険料をつみたてNISAやiDeCoなどの投資に回すことで、長期的には資産形成の効率が高まります。
③ ライフステージに合わせやすい
子育て世代など「一定期間だけ保障がほしい」人にはぴったり。必要なときに、必要な分だけ保険を持てるのが魅力です。
3. 掛け捨て保険のデメリット
① 解約してもお金は戻らない
いちばんのデメリットはここ。保険期間が終了しても、満期金や返戻金が一切ないため、保険料が「無駄に見える」ことも。
② 長期間加入するほどトータルコストが高くなる可能性
例えば、終身保険は保険料が高い分、将来的に戻ってくる金額があり、トータルで損得を判断する必要があります。
③ 加入時の年齢や健康状態で保険料が変動
掛け捨て保険は更新制のものも多く、更新ごとに保険料が上がるケースも。年齢を重ねてから新規加入する際は注意が必要です。
4. 得する人とは?掛け捨て保険が向いているのはこんな人
無駄な保険料を極力払いたくない人
→必要最低限の保障で割り切れる人にはベスト。
若いうちから資産運用をしたい人
→浮いた保険料を投資に回して増やせる人。
子どもが独立するまでの保障だけ欲しい人
→「万が一」に備える期間が明確な人に最適。
保険料の安さを優先したい人
→月々の家計負担を最小限に抑えたい人。
5. 損する人とは?掛け捨て保険が不向きな人
保険を“貯蓄”と考えている人
→お金が戻らないことに不満を感じる可能性大。
一生涯の保障が必要な人
→医療や介護リスクを考えると、終身型の方が安心という人も。
更新型保険の仕組みを理解していない人
→将来的な保険料アップに驚く人が多いので注意。
6. 掛け捨てか?貯蓄型か?選び方のポイント
目的に合わせて選ぶ
- 「保障」目的 ⇒ 掛け捨て
- 「貯蓄・相続」目的 ⇒ 貯蓄型
家計のバランスで考える
- 余裕があれば貯蓄型、支出を抑えたいなら掛け捨て
他の資産形成手段とのバランス
- 「保険」と「投資」の役割分担ができているか?
7. 体験談:掛け捨てで得した人・損した人の実例
得した人(30代・会社員・男性)
子どもが生まれたタイミングで、10年の掛け捨て定期保険に加入。月2,000円の保険料で1,500万円の保障がつき、万が一の安心を確保。その分、浮いたお金で積立NISAを活用。将来的には終身保険よりリターンが大きくなりそう。
損した人(40代・自営業・女性)
掛け捨ての医療保険を20年近く継続。特に大きな病気もなく、トータルで支払った保険料は100万円超。「お金が一円も戻らないことに後悔。最初から貯蓄型にしておけばよかった」と話す。
まとめ|掛け捨ては「損」じゃない。使い方で未来は変わる!
掛け捨て保険は、「無駄」と思われがちですが、実は合理的な選択肢です。
大切なのは「何のために保険に入るのか」を明確にすること。
保障を“コスト”と捉えて、その分を他の資産形成に回せるなら、掛け捨て保険は“得する”選択になります。
株式会社GRASIMのがん対策への取り組み
弊社は、厚生労働省が推進する「がん対策推進企業アクション」に賛同し、推進パートナー企業として登録されています。
現代では、女性の社会進出や定年延長により、職場で働くがん患者の数が増加しています。私たちは、職域検診の推進やがん検診受診率の向上に努め、がんと前向きに取り組む社会づくりを目指しています。
がんはもはや『不治の病』ではありません
早期発見と適切な治療が重要です。
株式会社GRASIMは、『がん対策推進企業アクション』を通じてサポートを続けていきます



