はじめに
9月の第3月曜日は「敬老の日」。家族が健康や長寿を願う大切な日です。この機会に「親の医療費」や「介護費用」について考えてみるのはいかがでしょうか。特に高齢の親を持つ世代にとって、医療費の増加や将来の介護リスクは避けられない現実。そこで注目されるのが「シニア向け保険」です。本記事では、敬老の日に合わせて、親の医療保険の見直しや介護保険の必要性、高齢でも加入できる保険について包括的に解説していきます。
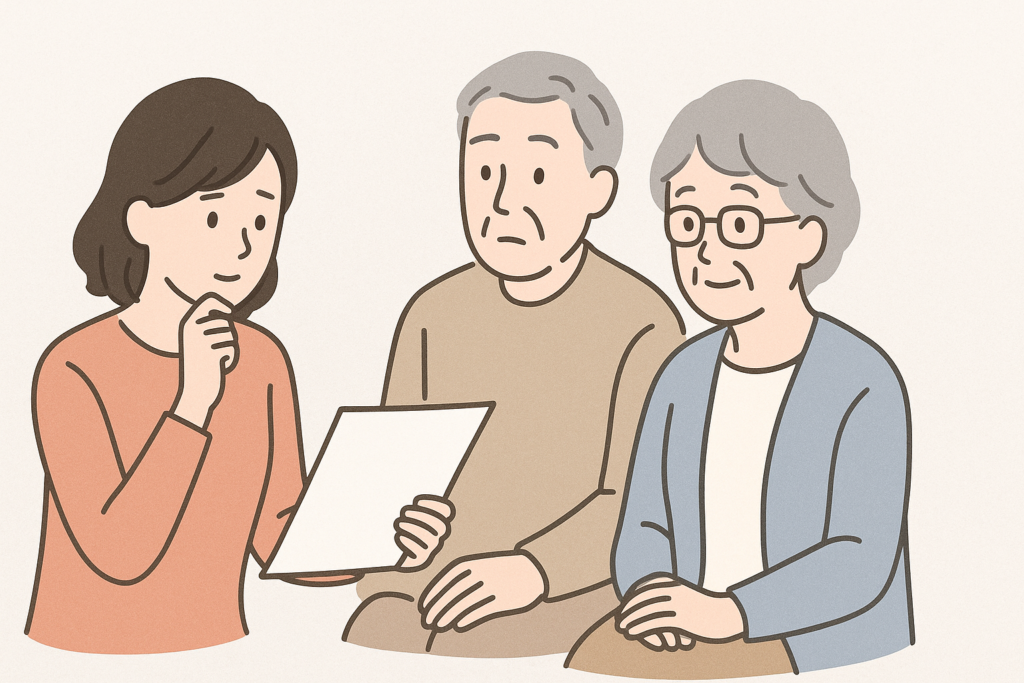
1. なぜ敬老の日に「シニア保険」を考えるべきなのか
敬老の日は、ただお祝いをするだけではなく「これからの暮らし」を見つめ直す良いきっかけになります。医療や介護の問題は、突発的に訪れることが多いため、事前の準備が欠かせません。
- 日本は長寿社会 → 平均寿命は延びても健康寿命との差が10年前後
- 高齢になると医療費・介護費用が増加 → 年間100万円を超えるケースも
- 公的保障だけでは不十分 → 自己負担が家計を圧迫
こうした背景から、「親に万が一があったときに備える」ことは、子世代にとっても重要な課題といえます。
2. 親の医療保険を見直すタイミング
高齢になるにつれ、医療保険の保障内容や保険料が生活に合わなくなることがあります。以下のタイミングで見直しを検討しましょう。
(1) 定年退職を迎えたとき
収入が減るため、高額な保険料を払うのが負担に。保障内容と保険料のバランスを調整すべき時期です。
(2) 持病が増えたとき
高齢になると病気が増え、既存の保険が使いにくくなることも。入院給付金や通院保障の有無を確認しましょう。
(3) 子どもが独立したとき
教育費がかからなくなったタイミングで、医療保障を手厚くしても良いでしょう。
3. 介護保険って入った方がいいの?
介護は誰にでも起こり得る問題です。介護保険に入るべきかどうか悩む方は多いですが、メリットとデメリットを整理してみましょう。
メリット
- 公的介護保険で賄えない自己負担をカバーできる
- 要介護状態になったとき、一時金や年金形式で給付を受けられる
- 子どもに経済的負担をかけにくい
デメリット
- 高齢になると保険料が高額になりやすい
- 加入時に健康状態の審査がある
- 実際に介護が必要にならなければ給付を受けられない
👉 ポイントは「親の年齢」と「家計の余裕」を見極めること。60代前半までに加入するのが理想です。
4. 高齢の親でも加入できる保険はある?
「70歳を超えているからもう保険に入れないのでは?」と不安に思う方も多いですが、近年は高齢者でも加入できる保険が増えています。
(1) 引受基準緩和型保険
持病があっても入りやすいのが特徴。告知項目が少なく、通院中でも加入できるケースがあります。
(2) 無選択型保険
健康状態の告知不要。ただし、保険料が割高で保障も限定的になることが多いです。
(3) シニア専用医療保険
70代や80代でも加入可能な商品も登場。入院や手術だけでなく、先進医療までカバーするケースもあります。
5. 子世代が知っておきたい「親の保険との向き合い方」
親世代は保険の契約内容を把握していないことが多いため、子ども世代がサポートすることが大切です。
- 保険証券を確認して内容を把握する
- 保険料の支払いが負担になっていないか確認
- 医療・介護の備えが不足していないか話し合う
👉 敬老の日は「ありがとう」を伝えるだけでなく、将来に向けて親子でお金や保険の話をする良い機会になります。
6. シニア保険選びのチェックポイント
シニア向けの保険は種類が多く、選び方が難しいものです。以下のポイントを押さえて検討しましょう。
- 加入可能年齢は?(70代・80代でも入れるか)
- 保険料は生活に負担にならないか
- 入院・通院・手術の給付条件は?
- 介護になったときに給付があるか
- 解約返戻金や保障期間を確認
まとめ
敬老の日は、家族の絆を深める日であると同時に「これからの暮らし」を考える大切な節目です。親の医療費や介護費用は、誰にとっても避けて通れない問題。今からシニア保険を見直し、家族が安心して暮らせる未来を準備していきましょう。
株式会社GRASIMのがん対策への取り組み
弊社は、厚生労働省が推進する「がん対策推進企業アクション」に賛同し、推進パートナー企業として登録されています。
現代では、女性の社会進出や定年延長により、職場で働くがん患者の数が増加しています。私たちは、職域検診の推進やがん検診受診率の向上に努め、がんと前向きに取り組む社会づくりを目指しています。
がんはもはや『不治の病』ではありません
早期発見と適切な治療が重要です。
株式会社GRASIMは、『がん対策推進企業アクション』を通じてサポートを続けていきます



