がん治療は、治療方法・期間・進行度によって費用が大きく変わります。
「保険でどこまでカバーされるのか?」
「自己負担はいくらになるのか?」
といった疑問は、多くの人が知りたいポイントです。
本記事では、2025年時点の制度や保険の仕組みを踏まえながら、がん治療で保険が適用される範囲と実際の負担額をわかりやすく整理します。
医療費の仕組み、健康保険・高額療養費制度の実例、がん保険の給付金や先進医療の注意点まで、初めての方でも理解できる内容にまとめました。
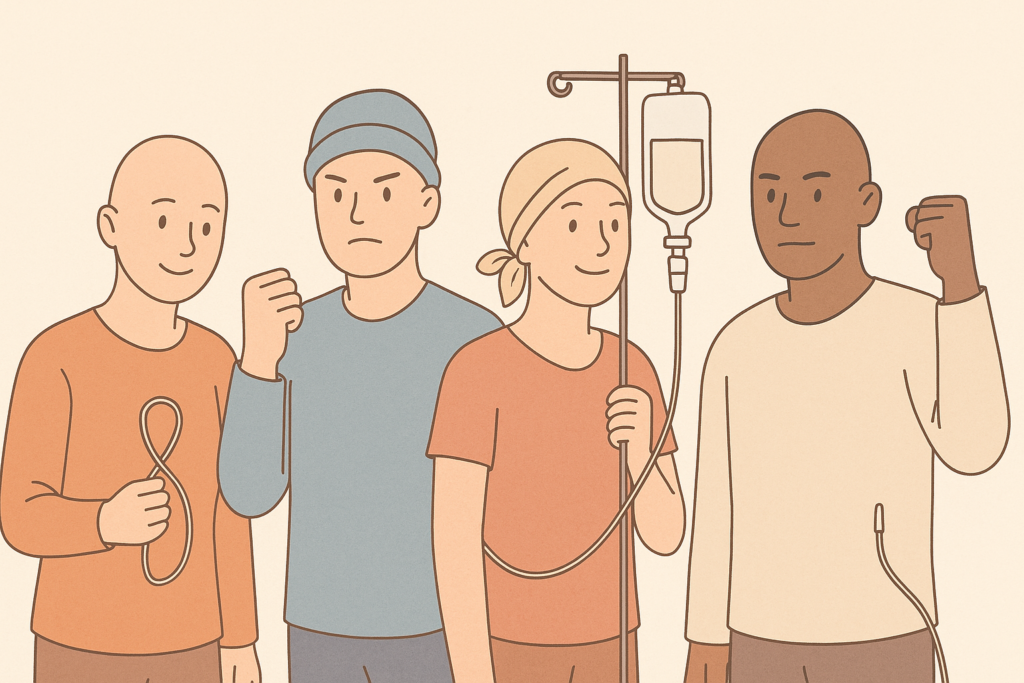
■1. がん治療は“多くの部分で保険適用される”が、例外もある
結論から言えば、がん治療の多くは健康保険の対象です。
日本は国民皆保険制度のため、標準治療(エビデンスに基づいた治療)であれば、ほとんどが保険適用になります。
●保険適用になる主な治療
- 手術
- 放射線治療
- 抗がん剤治療
- ホルモン療法
- 緩和ケア(医療行為がある場合)
- 入院費・検査費用
これらは自己負担は1〜3割で済みます。
しかし、近年増えている「自由診療」や「先進医療」は例外で、保険が効かないため費用が跳ね上がります。
■2. 健康保険でカバーされる範囲を“治療内容別”に解説
●(1)手術費用
がん治療の多くの手術は保険適用です。
自己負担は約10〜30万円前後になることが一般的ですが、高額療養費制度を使えばさらに下がります。
●(2)抗がん剤治療
抗がん剤は種類によって価格差が非常に大きいですが、標準治療に該当すれば保険適用されます。
例:分子標的薬
- 自己負担なしの場合の薬価:約30〜50万円/月
- 3割負担でも約10〜15万円
※高額療養費制度を使用すれば、後述の限度額以内に収まるケースがほとんど。
●(3)放射線治療
放射線治療も保険適用。
1回1万円前後(3割負担の場合)
20〜30回照射するケースが一般的で、負担は一定の上限に収まります。
●(4)緩和ケア
疼痛管理や薬物療法が伴う緩和ケアは保険対象。
ホスピス入居の場合は保険外費用も増えるため注意が必要です。
■3. 健康保険ではカバーされない“自由診療”と“先進医療”
近年、がん治療の選択肢が多様化し、自由診療が増加しています。
これらは保険対象外で、費用が高額になりやすい点が問題です。
●(1)自由診療の例
- 免疫細胞療法
- 樹状細胞ワクチン
- 温熱療法(ハイパーサーミア)
- 海外での治療
これらは数十万〜数百万円かかることも珍しくありません。
●(2)先進医療
保険治療との併用はOKですが、先進医療部分の費用は全額自己負担です。
代表例:重粒子線治療
- 費用:約280万円
- 保険適用は一部のがんのみ
先進医療は高額なため、がん保険の「先進医療特約」が役立つケースが多いです。
■4. 医療費の自己負担を大幅に抑える「高額療養費制度」
がん治療の負担を大きく減らす制度が「高額療養費制度」です。
これは1か月の医療費の自己負担に上限を設定する仕組みです。
●上限の目安(現役並み所得の人)
- 約8〜9万円前後/月
たとえば、抗がん剤治療で15万円かかった場合でも、実際の負担は上限以下に収まります。
●限度額認定証を使えば“窓口支払いも上限だけ”に
後から申請すると払い戻しですが、限度額認定証を使えば最初から上限額のみの支払いで済みます。
■5. がん保険でカバーされる範囲(2025年版)
健康保険だけでは不安を感じる人の多くが、補完として「がん保険」に加入しています。
がん保険がカバーする主なものは以下です。
●(1)診断一時金
- 50万〜100万円が一般的
- 初期費用として最も役立つ給付
●(2)通院給付金
通院1日あたり:5,000〜1万円
抗がん剤治療で長期間通う場合に非常に有効です。
●(3)先進医療特約
- 先進医療の費用(〜300万円程度)を全額カバー
- 月100円〜200円で付けられる
●(4)入院給付金
1日5,000〜10,000円
治療が長引いた場合にも安心。
●(5)収入補償タイプ
働けない期間の収入減を補うもの。
がん治療は治療費よりも「収入減」の方が家計に響くという実態もあり、人気が高い。
■6. “保険で何がどこまで出るか”を実例で解説
◆ケース:抗がん剤治療+通院
- 抗がん剤治療費:15万円
- 自己負担(限度額制度あり):約8万円
- がん保険の通院給付:3万円
- 診断一時金:50万円
→ 差し引き負担は実質マイナスになるケースも多数
◆ケース:重粒子線治療(先進医療)
- 費用:280万円(自己負担)
- 先進医療特約あり:280万円全額カバー
- 実質負担:ほぼゼロ
■7. 治療費を抑えるために今できること
●(1)限度額認定証を必ず取得
長期治療では必須。
●(2)自由診療は慎重に
口コミだけで判断しない。
●(3)がん保険の“実費補償型”を検討
治療費の変化に強いタイプ。
●(4)セカンドオピニオンで過剰医療を防ぐ
医療の質を保ちつつ、無駄な費用を削減。
■まとめ:保険で“ほとんどカバーできる”が、カバー外の治療に注意
がん治療の多くは健康保険と高額療養費制度でカバーされます。
しかし、自由診療・先進医療・長期的な収入減など、保険では埋めきれない部分が存在します。
その不足分を補うために、がん保険や収入補償が重要な役割を果たします。
治療費の不安を減らす最大のコツは、制度の仕組みを理解し、“保険でカバーされる治療”と“されない治療”を正しく見極めることです。
株式会社GRASIMのがん対策への取り組み
弊社は、厚生労働省が推進する「がん対策推進企業アクション」に賛同し、推進パートナー企業として登録されています。
現代では、女性の社会進出や定年延長により、職場で働くがん患者の数が増加しています。私たちは、職域検診の推進やがん検診受診率の向上に努め、がんと前向きに取り組む社会づくりを目指しています。
がんはもはや『不治の病』ではありません
早期発見と適切な治療が重要です。
株式会社GRASIMは、『がん対策推進企業アクション』を通じてサポートを続けていきます



