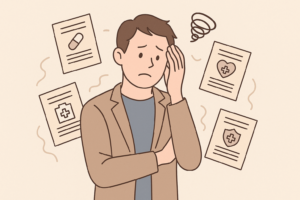はじめに:「貯金だけ」では将来が不安な理由
多くの人が「貯金さえしておけば安心」と考えがちですが、実はそれだけでは将来の資産形成において不十分なこともあります。物価の上昇(インフレ)や低金利時代において、お金の価値は時間とともに目減りしていくからです。
たとえば、銀行に100万円を預けていても、10年後の物価が20%上昇していれば、実質的にその価値は80万円と同じ。だからこそ今、**「増やすための貯金=資産運用」**が必要なのです。

第1章:資産運用とは?初心者でもわかる超基本
資産運用とは、自分の持っているお金を「働かせて増やす」行動のことです。以下のような目的で行われます。
- 将来の老後資金を準備したい
- 子どもの教育費に備えたい
- 結婚やマイホーム購入などライフイベントの資金を増やしたい
資産運用といってもギャンブルではありません。リスクとリターンのバランスを考え、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
第2章:初心者におすすめの資産運用5選
1. 積立NISA(少額投資非課税制度)
- 少額(月100円〜)から投資可能
- 利益が非課税になる制度(最大20年間)
- 投資信託を自動でコツコツ積み立てられる
初心者には最も始めやすい制度です。まずは「eMAXIS Slim」などのインデックス型ファンドから始めるのが王道。
2. iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 老後資金のための私的年金制度
- 掛金が全額所得控除 → 節税効果が大きい
- 原則60歳まで引き出せない=長期投資に向いている
「老後資金を着実に作りたい人」に特におすすめ。
3. ロボアドバイザー(例:WealthNavi、THEOなど)
- 資産運用をプロのアルゴリズムに任せられる
- 自動でリバランス&再投資してくれる
- 資金を入れるだけでOKなので、手間なしで楽に運用
仕事が忙しい人・知識に自信がない人には最適。
4. 定期預金+国債(超低リスク)
- リスクが限りなくゼロに近い
- 銀行預金よりやや高い利回り(0.05〜0.1%程度)
リターンは小さいが、「まずは安全に資産を守りたい」という人向け。
5. 株式投資(中〜上級者向け)
- 配当金や値上がり益が期待できる
- NISAや特定口座を活用すれば節税可能
- 銘柄選びとリスク管理がカギ
学ぶことが多いが、**興味がある人は「少額からのスタート」**を。
第3章:資産運用ステップバイステップ
Step 1|目標と目的を明確にする
「何のために、いくら増やしたいのか?」を明確にしましょう。
例)
- 10年後に300万円の教育費が必要
- 老後資金として月3万円を積み立てたい
Step 2|収支を見直して「運用資金」をつくる
収入・支出を棚卸しし、無理なく投資に回せる金額(例:月1万〜3万円)を設定。
Step 3|自分に合った運用方法を選ぶ
リスク許容度(年齢・性格・目的)に応じて、積立NISAやiDeCo、ロボアドを選びましょう。
Step 4|証券口座を開設する
以下のようなネット証券が初心者に人気です:
- SBI証券
- 楽天証券
- マネックス証券
Step 5|運用開始!定期的なチェックと見直しを忘れずに
年に1回は運用成績を確認し、必要に応じて「リバランス」や「積立額の見直し」を行いましょう。
第4章:初心者が陥りがちな3つの落とし穴
- 一気に投資しすぎる(タイミング依存)
→ 積立方式で「時間分散」を意識しましょう。 - SNS・YouTubeで見た「流行り」に飛びつく
→ 必ず「自分の目的」に合っているかを考える。 - リスクが怖くて始められない
→ ロボアドや積立NISAは「リスクが分散された商品」なのでまずは少額から挑戦。
まとめ:貯金だけじゃお金は増えない。動いた人だけが将来に安心を得られる
資産運用は決して難しいものではありません。大切なのは、「目的を持ち、コツコツ継続すること」。
貯金と並行して「お金に働いてもらう習慣」を今から取り入れることで、数年後の安心感は大きく変わってきます。
株式会社GRASIMのがん対策への取り組み
弊社は、厚生労働省が推進する「がん対策推進企業アクション」に賛同し、推進パートナー企業として登録されています。
現代では、女性の社会進出や定年延長により、職場で働くがん患者の数が増加しています。私たちは、職域検診の推進やがん検診受診率の向上に努め、がんと前向きに取り組む社会づくりを目指しています。
がんはもはや『不治の病』ではありません
早期発見と適切な治療が重要です。
株式会社GRASIMは、『がん対策推進企業アクション』を通じてサポートを続けていきます